AIがお問い合わせ文を自動作成
面倒な文章入力は不要。ポチポチ選ぶだけで、
あなたのご相談内容をAIが整理します。
もちろん、直接お問い合わせ文を入力することもできます。

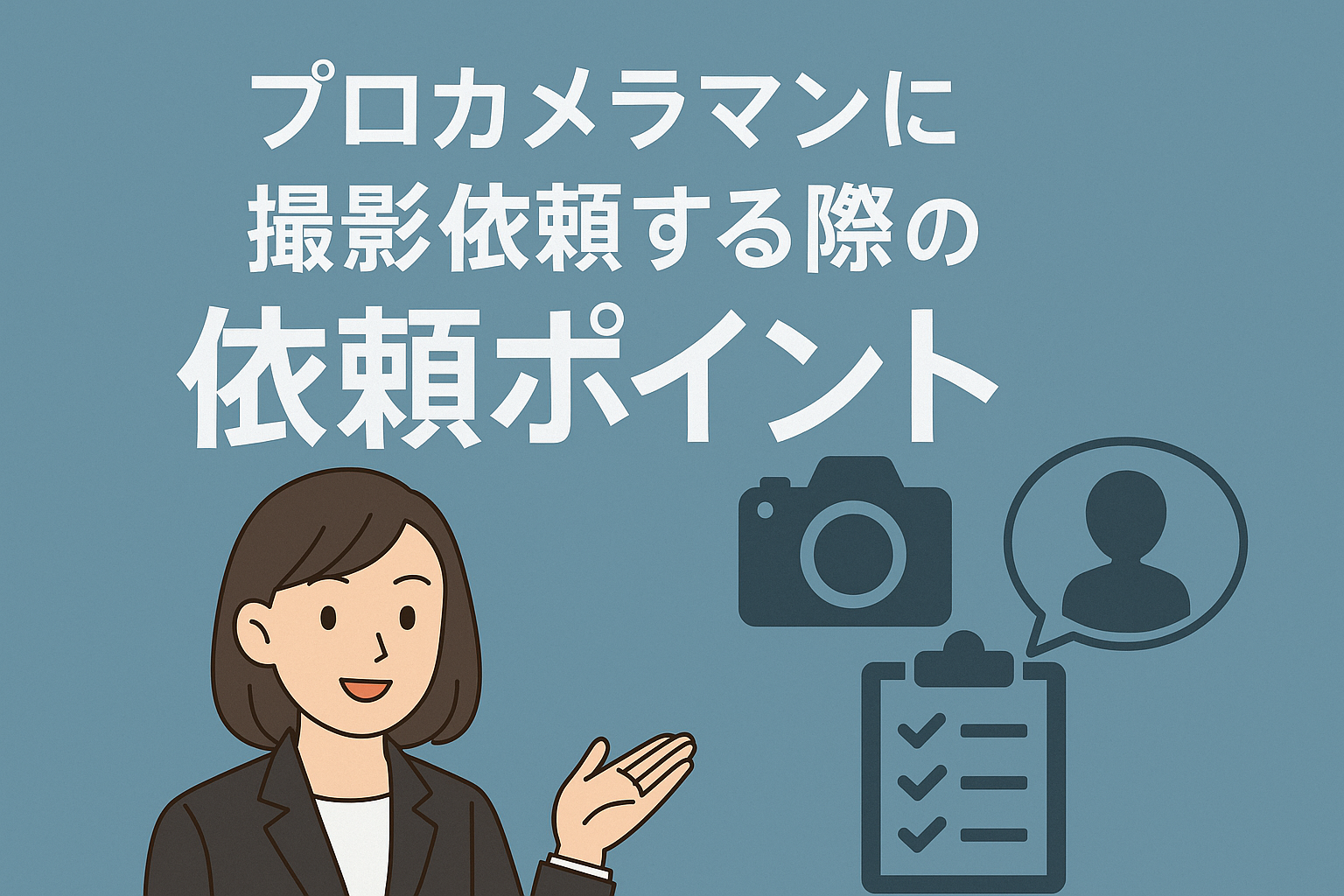
カメラマンは撮影のプロですが、被写体の背景や目的を知らなければ、企業が本当に伝えたいイメージは撮れません。 例えば「社内風景」でも、“温かみのある社風”を表現したいのか、“スタイリッシュで洗練された職場”を見せたいのかで撮り方がまったく異なります。
つまり、「何のために」「誰に向けて」「どんな印象を与えたいのか」を明確に伝えることが、外注撮影を成功させる鍵です。
この情報が揃っていれば、撮影の段取り・時間配分・必要な機材まで事前に調整でき、当日の進行もスムーズになります。
目的に応じて「写真の構成・順番」も変わってくるため、最終用途を必ず事前にカメラマンに伝えることが重要です。
→口頭では伝わりづらいため、「こういう雰囲気が理想」と分かる参考画像を事前に共有しましょう。
→必要なカットリストを事前に作成。事後に「○○の写真がない」とならないように、チェックリスト形式で共有するのが有効です。
→肖像権の観点から、事前に社内周知や同意取得を行いましょう。必要に応じてボカシ処理などの編集依頼も可能です。
→「JPG」「PNG」「TIFF」など用途に合った形式での納品を依頼時に明記。サイズ(px)・解像度(dpi)も忘れず確認しましょう。
撮影が終わったからといって油断は禁物です。使用に関してのルールを守りつつ、社内用・広報用・採用用など複数用途に転用できる写真を揃えておくと、次の業務がスムーズです。
当日は現場の流れや空気感によって予定が変わることもあります。だからこそ、現場を理解している社内スタッフの立ち会いが非常に重要です。
撮影に同行することで「撮れた写真=社内の希望通りか」をその場でチェックできます。修正指示が出せる唯一のタイミングです。
価格だけで判断せず、「誰がどんな写真を撮るか」まで確認することで、ミスマッチを防げます。
プロカメラマンへの撮影依頼は、ただ外注するだけでは不十分です。 成果物の質は、依頼側の「伝え方」「準備の質」で決まります。
特に、企業の広報写真や採用ページに掲載する写真は、ブランドイメージに直結します。妥協せず、しっかりと準備をして、最大限の成果を引き出しましょう。